
グループでテーマに沿って議論を行うことを「グループディスカッション」といい、テーマについて議論して回答を出し、グループの総意として発表するところまで行うことが多いです。
多くの学生を一度に見ることができるため就職活動でも使われていることが多く、中学生でもグループディスカッションを取り入れ学んでいきたいところですよね。
ここでは中学生に向けたグループディスカッションのテーマの紹介、そしてグループディスカッションを円滑に進めるためのコツや注意点などをまとめています。
今だけではなく将来の役に立つグループディスカッション、ぜひどのようなテーマが良いのか、何を注意して進めればよいのかをチェックしていきましょう!
グループディスカッションのやり方は?中学生が行うことのメリットは?
しかしグループディスカッションのやり方、また中学生が行うことによるメリットが分からないと取り組むことも難しいので、まずはやり方などをチェックしていきましょう。
グループディスカッションのやり方はまず最初に時間を決め、自己紹介をしてから役割を分担します(役割については後ほど紹介します)。
その後どのように時間を配分するのかを決め、意見やアイデアを出し合い整理し、それからグループとしての結論・総意としてまとめて発表できるように準備をすればOKです。
時間については多くの場合30~45分程度が多く、この時間内で結論が出せるように時間配分をグループ内で考えることもグループディスカッションでやることのひとつです。
グループディスカッションの役割
司会・進行
グループで議論を行うためにも進行役を作ることは大切で、決してリーダーではなく全体を見通し、発言できていない人がいないか、意見を言いたくても言えない人がいないかなどを確認します。
リーダーというよりは心配りができる、発言しやすい状況を作る役割といったほうが正しく、全体を見てフォローできるようなタイプが向いています。
時間管理
議論が盛り上がりすぎて気がつけばまとめる時間や、発表の準備の時間がなくなってしまった、ということを防ぐのが時間管理で、進行役のサポート的な立ち位置になります。
自分が熱くなって時間を忘れる、盛り上がりすぎて時間が押していることを言い出せないなどしてしまうと失敗になるので、常に冷静な目を持てるタイプが向いています。
書記
議論がどれだけ盛り上がってその中で良い意見が出たとしても、記録していなければうっかり忘れてしまったということも起こるため、要点をまとめておく書記も大切な役割になります。
またもちろん要点を書くことに集中しすぎて自分の意見を言わないというのはNGで、自分の意見もしっかり出しつつ要点をまとめられる方が向いています。
役割についていないからといって、決して役割がないから気楽と考えるのは間違いで、むしろその他の方が積極的に場を盛り上げディスカッションしていくことがグループ全体にも大切です。
グループディスカッションはこのような役割を決めて最低3名、多くて10名程度のグループに分けて議論を行うため、参加する人数を考慮しグループを分けていきましょう。
その際できるだけ幅広い意見をグループ内で持ったほうが良いので、できれば男女均等に、意見が違うタイプを同じグループに入れる方法がおすすめです。
中学生でグループディスカッションを取り入れるメリットとしては将来への準備はもちろん、議論することにより自分とは違う意見があることも知れ、それをまとめる能力なども身につけられます。
また日頃あまり発言しない、人に流されることが多いという生徒も少人数のグループディスカッションに参加することで発言できる環境を作ることが出来ます。
グループディスカッション中学1年生おすすめ5選!

グループディスカッションのテーマは数多くあるものの、その中でも中学1年生におすすめのテーマをいくつか紹介していきます。
1.「無人島にひとつだけ持っていくなら何にする?」
中学1年生の場合難しいテーマを選ぶよりも、一度自分でも空想したことがあるような、それでいて多くの場所で採用されているテーマを選ぶと盛り上がりやすいです。
2.「ドラえもんのひみつ道具でほしいもの」
日本で暮らしていると必ず知っていると言っても過言ではないドラえもんのひみつ道具でほしいものを一つ選び、なぜそれが欲しいのか、メリットやデメリットを考える方法もおすすめです。
3.「桃太郎に登場する動物で一番有能なのは?」
これもグループディスカッションで広く使われているテーマのひとつで、誰もが知っている物語である桃太郎を題材に、なぜその動物が有能だと思ったのか、明確な理由も議論していきましょう。
4.「仲直りの方法は?」
友達同士が喧嘩をしてしまった場合どうすれば仲直りができるのか、間に立った自分に何ができるのかという生活に沿ったテーマとなり、考えやすいです。
5.「朝食はパンかご飯どちらが良い?」
これも生活に沿ったテーマで、どちらにもメリット・デメリットを出しやすくなっていて中学1年生のテーマとして使いやすくなっています。
グループディスカッション中学2年生おすすめ5選!

次に中学2年生向けのグループディスカッションのテーマを紹介していくので、中学2年生のディスカッションのテーマにお悩みの方はぜひご確認ください。
1.「親友・恋人・お金の優先順位は?」
人間関係が複雑になる、大人の社会もちょっとずつ見えてくる中学2年生におすすめのテーマで、なぜその優先順位にしたのかなども議論にしやすいです。
2.「ダイエットは食事制限とトレーニングどちらが良いか」
特に女子はダイエットなども気になる年齢になってくる、部活などでトレーニングの必要性やメリットなども学ぶ年頃であると、こちらも理論に基づいた議論をしやすいテーマですね。
3.「ドラえもんのひみつ道具を新しく作るなら?」
中学1年生のテーマではドラえもんのひみつ道具でほしいものというテーマを紹介しましたが、中学2年生はさらに一歩進み、新しいひみつ道具を考えるのもおすすめです。
4.「ディズニーランドとUSJ、どちらに行く?」
住んでいる場所で結論が違う可能性があるもののそれもまた議論の一つにできるため、中学生が関心を持ちやすいテーマパークをテーマにする方法もおすすめです。
5.「タイムマシンで過去と未来どちらに行きたい?」
こちらも歴史が授業にある程度取り込まれた中学2年生におすすめのテーマで、また選んだ理由やどちらが良いかという議論もしやすく、テーマとして扱いやすいです。
グループディスカッション中学3年生おすすめ5選!

最後に中学3年生向けのグループディスカッションのテーマをいくつか紹介していくので、こちらもぜひご確認ください。
1.「大学には行くべきか」
中学3年ともなれば進路や自分の将来を考える年頃なので、こういった年代に沿った進路のグループディスカッションは盛り上がりやすくおすすめです。
2.「テレビとYou Tubeどちらが良い?」
現在は中学生もスマホを所持していることが多くYou Tubeも見ている生徒が多いため、テレビとYou Tubeどちらが良い、どちらが有益かなどもテーマに使いやすくなっています。
3.「コンビニは24時間営業が必要?」
少し前にコンビニエンスストアの24時間営業について世間でも騒がれましたが、コンビニの24時間営業は本当に必要かという議論も生活に沿ったテーマで使いやすいですね。
4.「何歳まで生きたい?」
ちょっと抽象的で難しいテーマになりますが、何歳まで生きたいか、またそれはなぜかというのも生活や周囲を見ながらの議論ができるのでおすすめです。
5.「生まれ変わったらなりたい動物は?」
人間以外に生まれ変わった場合になりたい動物を議論するのもテーマとして考えやすく、また個人によって様々な意見がでるためおすすめです。
グループディスカッションを円滑にすすめるコツは?注意点は?
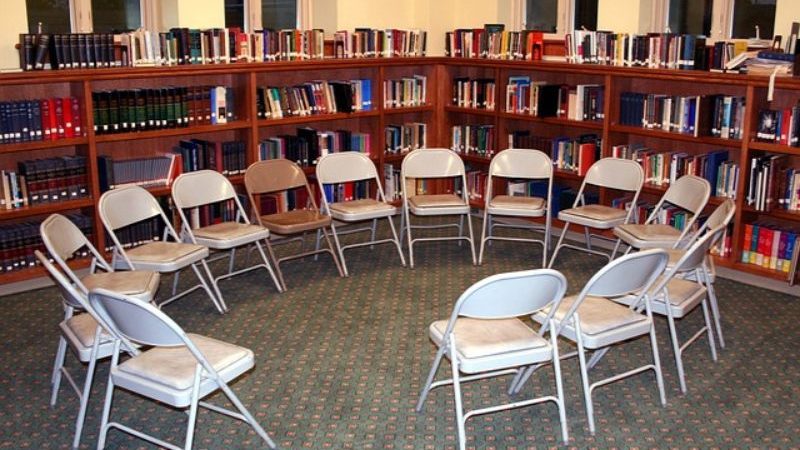
時間が過ぎてしまった、それならまだしも喧嘩になってしまった、結論がまとまらないなどのトラブルもグループディスカッションではよくあるので、注意点やコツもチェックしていきましょう。
少人数で議論をする、ましてや意見が合わない相手とも議論しひとつの総意としてまとめなければならないというのはどうしてもトラブルが多くなります。
また日頃からあまり発言しない、自分の意見を言えない生徒の場合はグループディスカッションでも発言しにくく、その結果目立つ生徒の意見が採用されてしまうなども考えられますね。
こういったトラブルを回避するためにもいきなりグループディスカッションに入るのではなく、その前にちょっとした雑談タイムを入れ、お互いの性格などを把握しておくことが大切です。
このタイミングではテーマなどを深く考える必要はなく、同じクラスでもあまり話したことがなかった相手とも事前に話し、会話ができる空気を作っておきましょう。
またグループディスカッションで大切なこととして「他人の意見を否定しない」というものがあり、つい熱くなると自分の意見を通したく相手を否定してしまいがちですが、これはいけません。
グループディスカッションの目的はグループの総意として結論を出すことにあるので、否定するのではなくなぜその意見ではダメなのか、どうすればよいのかを議論しましょう。
これを参加者が理解し気をつけていれば喧嘩になることもなく、また自分では考えられなかった理論や展開により相手の意見のメリットにも気付かされるなど良いポイントがたくさんあります。
「結論がまとまらない」という失敗もグループディスカッションではよく聞きますが、これはなぜかというと進行役や時間管理をしっかり決めていないからというのが多いです。
グループディスカッションの役割のところでもお話した通り開始前に役割をしっかり決め担当者が注意しておくことで回避しやすくなるので、これも開始前に再度確認できると良いですね。
まとめ
中学生におすすめのグループディスカッションのテーマ紹介、グループディスカッションをスムーズに進行させるためのコツや分担などまとめ!
グループディスカッションは難しく考える必要はなく「アイデアを出し合いまとめるもの」「様々な意見を知るきっかけ」として取り入れる方法が中学生としてはおすすめです。
何度も繰り返していくとグループディスカッションにも慣れ将来の準備にもなるので、ぜひ様々なテーマを用意しグループディスカッションで盛り上がっていきましょう!






















